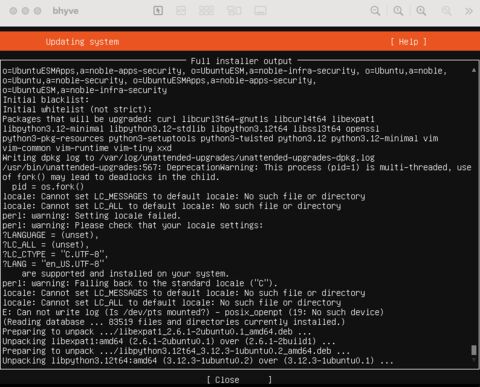2024/09/29(日)bhyveでk8s - #1 fedoracoreos
参考情報
参考情報をみてやるだけ、ではある。 https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/virtualization/#virtualization-host-bhyve https://forums.freebsd.org/threads/hints-for-installing-fedora-in-bhyve.80257/
目論見
- 管理ノードを3台で構築する。
- ワーカーノードを2台くらい作る。
- なんか乗せる。
余力で
- bhyve で node のスケーリングってできる?
- ignition を 動的に作成できないか
- 人の手で構築するのはナウくない気がする
やってみるとクラウド環境って便利。自動化とかスケーリングとか当たり前にある前提だけどローカルにそれらはない。kind とか minikube 使わずコントロールプレーン側を触ってみるのが目的なので不便は承知。
作業
bhyve 環境は出来ている前提
Fedora CoreOs の準備
Live DVD をダウンロードしておく https://fedoraproject.org/
ディスクを作る
散らからないように階層を掘ってボリュームを作る。例では k8s という階層にまとめた。
sudo zfs create -o mountpoint=none stor/k8s sudo zfs create -V 16G stor/k8s/coreos01 sudo zfs create -V 16G stor/k8s/coreos02 sudo zfs create -V 16G stor/k8s/coreos03
ネットワークインタフェース作成
bridge インターフェースはbhyve環境として準備されている前提。
sudo ifconfig tap create sudo ifconfig bridge addm tap0
ignition ファイルを作る
- fedoraCoreOSは初期設定を ignition ファイルで指定するらしい
- yaml で書いて、butane というツールで json に変換するらしい
- なぜ変換を介在させるのかはよくわからない
- テンプレートエンジンを持っているとか器用なことができるわけではない
ファイルを用意
- ssh 公開鍵を置く
- 2つあるのはbhyveホストと普段の生活環境PCの分
- IP アドレスを指定する
- DHCP側でIPアドレスを固定できるならその方が楽かも
- hostname って NetworkNodemanager の設定で指定できないの?
- ファイルは http で公開する
- 署名付き S3 とか
- ローカルHTTPサーバとか
variant: fcos
version: 1.5.0
passwd:
users:
- name: core
ssh_authorized_keys:
- ecdsa-sha2-nistp521 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHA1MjEAAAAIbmlzdHA1MjEAAACFBAGbIdk/TcXdtEmKo7MgQGmhOKmaZgxGG8YXzWUP84yx1yI44YOlGUgSez4aR5JoJ40XdoyNJY6eJyN== BSD
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5A mac
storage:
files:
- path: /etc/NetworkManager/system-connections/enp0s2.nmconnection
mode: 0600
contents:
inline: |
[connection]
id=enp0s2
type=ethernet
interface-name=enp0s2
[ipv4]
dns=192.168.3.1
gateway=192.168.3.1
address1=192.168.1.1/22
method=manual
このファイルを butane で ign ファイルに変換する。適当に Linux VM を用意して実行する。
https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora-coreos/producing-ign/#_via_a_container_with_podman_or_docker
インストーラーの起動
こんな具合のスクリプトを使って Fedoracoreos のLiveDVDを起動する。 fbufのパスワードが指定してあるのは、指定なしだと接続できなかったため。mac の 画面共有アプリのせいなのかどうなのかは未確認。
while ループに入れているのは、ゲストOSの再起動時にも bhyve が終了してしまうので。bhyve の戻り値はゲストの終了の仕方によって決まっていて、再起動のときは 0 が返る。
CoreOS は自動で更新して自動で再起動するが、bhyveコマンドをループさせておかないとこのタイミングでVMが終了してしまう。
while [ $? -eq 0 ]; do bhyve -A -H -P -c 2 -m 2048M \ -s 0:0,hostbridge \ -s 1:0,lpc \ -s 2:0,virtio-net,tap0 \ -s 3:0,virtio-blk,/dev/zvol/stor/k8s/coreos01 \ -s 4:0,ahci-cd,/pub/ISO/Linux/FedoraCoreos/fedora-coreos-39.20231119.3.0-live.x86_64.iso \ -s 29,fbuf,tcp=0.0.0.0:5900,w=800,h=600,wait,password=pass \ -s 30,xhci,tablet \ -l bootrom,/usr/local/share/uefi-firmware/BHYVE_UEFI.fd \ fedoracore01 done
mac では 画面共有 (Screen Sharing.app) で VNC 接続できる。とりあえずは Installing CoreOS on Bare Metal に従ってインストールする。
https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora-coreos/bare-metal/
起動したらインストーラーコマンドを実行する。
sudo coreos-installer install /dev/vda \ --ignition-url https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/ign.teak.jp/k8smaster01.ign?response-content-disposition=inline&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEAkaDmFwLW5vcnRoZWFzdC0xIkcwRQIh...
この後に続く kubeadm とかの設定が面倒そうだなぁ、と思っている。